
トラバス所属の行政書士、阪本です。
さて、運送会社の行政処分の中で、車両停止処分というものがあります。ナンバーを持っていかれてします行政処分です。
この際に、
- 停止車両のナンバープレートは、どうやって持っていかれるのか
- 停止期間が終了したときは、どのようにナンバープレートを取り付けるのか
といったご質問を私の関与先の運送会社さんよりご相談を頂きますので、このページではそれらの取扱についてご説明したいと思います。
営業所に15台の貨物自動車を配置している運送会社が、運輸局が実施した監査の際に、運転者3名の健康診断未実施の指摘を受けたことを想定事例といたします。
健康診断未実施は、『疾病、疲労等のおそれのある乗務』の違反行為として、初違反の場庵は車両停止40日車の行政処分とすると定められております。
車両が15台の営業所が40日車の行政処分を受けた場合、停止車両は2台となります。その2台の車両は40日車÷2台=20日車、つまり20日間ずつ運行することができなくなります。
(この車両停止期間の処分日車数及び事業用自動車数の詳しいことは、当ブログの「処分日車数制度」をご覧ください。)
車両停止処分はどのように実行されるのか
どのように車両停止措置を行い、車両停止期間が終了したら、どのようにナンバープレートを取り付けるのでしょうか。
神奈川運輸局管内では次のような流れで行われます。
- 行政処分の当該車両が決定される。
- 車両停止開始日に運送会社が前後のナンバープレートを外し(後ろの封印も運送会社が外します)、車検証と一緒に運輸支局に持っていく。
- 車両停止が開始される。
- 車両停止期間が終了。
- 運送会社が市区町村より仮ナンバープレートを借りて、車両停止車両に取り付ける。
- 仮ナンバープレートを付けた車両を運送会社が運輸支局に持ち込む。
- ナンバープレートと車検証が返却される
- 運送会社ナンバープレートを取り付けて、後ろのナンバープレートに再封印を行う。
行政処分の車両停止の手続きの流れは、以上のようになります。
ただし、上記の流れは停止車両が少数の場合であって、停止車両が多数の場合は事業所にて車両停止手続きをする場合もあります。
停止期間に動いていないかの確認は、運輸局の監査官がオドメーター(総走行距離メーター)を記録し、車両停止期間中にオドメーターが動いていないか(走っていないか)を確認する方法で車両停止処分を行う場合があります。
車両停止の行政処分を受けてしまうと、停止期間中は該当車両は運行できないため売上は下がります。しかし、運転者の給与は支払う必要があるため、運送会社の経営が厳しくなります。さらに、ナンバープレートや車検証の提出・引き取りで運輸支局へ行き来する手間と時間で、想像以上に運送会社の経営にダメージが大きいです。
車両停止処分を受けないためには
一般監査の場合、法令遵守が徹底されている運送会社であるならば、車両停止の行政処分を受けることはないと思います。車両停止処分を受けないためには、月並みですが、当たり前のことをしっかりやることが大事だと考えます。
なお、トラバスでは「法令順守状況アドバイザリーサービス」を提供しております。監査が実施されて車両停止処分の行政処分を受けてしまうと、運送会社に経営に大きなダメージを受けてしまいます。監査対応でご不安な点などがございましたら、監査が実施される前に私どもにご相談ください。
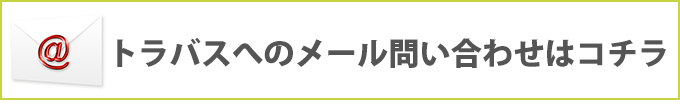
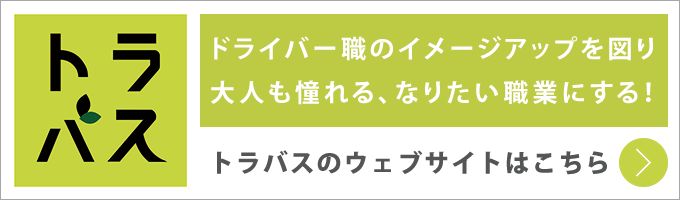
関連記事
トラバス代表理事。行政書士開業後、個人事務所時代から一貫して、運輸と観光分野に関する専門家として、数多くのトラック運送会社、貸切バス事業者、倉庫業者の許認可法務に関与してきた経験を持つ。
現在も行政書士法人シグマの代表行政書士として、行政書士法人を経営しながら、運輸業と観光法務の実務家として活動中。
一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)賛助会員(認定アドバイザー)




